【2020年7月2日】日本フォーム印刷工業会(フォーム工連)は6月2日、「2020年度 通常総会」を開催。ここで、12年間、フォーム工連の専務理事を務めた山口実氏が退任した。

フォーム工連といえば、時代の最先端を行く人物を講師としたセミナーや、ユニークなワークショップの開催で知られている。その仕掛人が山口氏だ。
同団体には「寺子屋プロジェクト」という企画もある。これはフォーム工連会員以外も、同団体のセミナーに参加できる、文字通り「寺子屋」として機能している企画。実は、この価格ができる以前から、山口専務理事の紹介で聴講生のように参加できるシステム(?)があり、その情報発信力と幅広い人とのつながりは、業界内外から高く評価されてきた。
今回は退任にあたり、山口氏に12年間の活動を振り返り、業界への贈る言葉をいただいた。
――日本フォーム工連、関東フォームの専務理事12年間で常に意識されたことをお聞かせください
私が専務理事となったのは2008年。
その後リーマンショックが起こり、企業の社会的存在意義や人が働くことへの意義が問われる時代になりました。その中で、スマートフォンやタブレット端末などが出現。一方で、印刷業はデジタル化による衰退が言われてきました。

その印刷産業に「『未来への希望』を与えるには何が必要か?」という問い掛けへの回答を目指し活動を行ってきました。
海外情報(ニュースサイト『What They Think』)はもちろん、印刷産業としての周辺ビジネスも紹介しました。伝えてきたのはBPOやロボット・人工知能、ファシリティマネジメントなど。また、業界ができる連帯の活動という点では、ISO共同取得や、ケースメソッドによるコンプライアンスへの取組み、小グループによる印刷技能教育、マネジメントゲームによるMQ管理会計など、多岐にわたりました。
フォーム印刷業界は、帳票や請求書、ダイレクトメールなどを扱う4500億円規模という分野です。ただ、その位置づけやブランド力は、世の中から見たらどうでしょう?この位置づけを向上していくことも考え、会員の方たちには「ブランド力と希望を持っていただけるような活動に」という思いで、テーマとさまざまな活動を提案し決めていきました。
印刷分野そのもののやることはかわっていないというのも感じています。
例えば、東日本大震災の後、被災者関連のさまざまな事後処理はフォーム業界が手掛けていました。今回の新型コロナウイルスでも同じでしょう。
最後には、住所や名前、関連データを印刷して、確かにその人に届けるという作業があります。

日本の印刷業界は、デジタル化とそのデータを扱うという意識は遅れていたにもかかわらず、生き残ってきた面があります。しかしこれも、今回の新型コロナウイルスの感染拡大により、1年後にはガラリと変わっていくかもしれません。
――フォーム工連といえば、先進的な講演会・セミナー、ワークショップが名物になっていました。あればどのような思いで開催されていたのでしょうか
テーマを決めるときに気にしたのは、「その時代に即した内容」というのもそうですが、「どのような方が聞きに来るか?」ということです。
大手企業であれば自社で有名講師を招いて社員教育を行うことができますが、フォーム工連の会員さんのうち約60%は200名以下の規模の企業です。
その方たちに、その時の社会情勢をウォッチし、各年で一番必要と感じていることをテーマに講師を選定しました。講師さんはだいたい私のツテを頼ってお招きしていました。
いろいろやりましたが、最近の講演会ではこんなことを意識しました。
「時代は変わるのに、経営者は変わらない、働いている社員も大きくは変わらない」と。厳しいことを言えば、大手企業の社員が「社名におぼれる」ということもそこにはあるでしょう。
人脈と呼んでいるものや、予算、設備も、そこ(大企業)に雇われているから行えるということがある。「これは実力じゃないんじゃないか?」と気が付けばいいのですが、なかなかその機会は訪れない。
そこで「自己ブランディング」というテーマを、最後の2年間は一生懸命やりました。
そんなことをしたら「社員がどこかに行ってしまうかも?」と経営者は思うのか、他で十分活躍できる人材が、自己ブランディングせずに埋もれているケースもあると私は思っています。

マネジメントゲームによるMQ管理会計のワークショップ
「MQ管理会計」というマネジメントゲームのワークショップを行ったのも、社員の方に経営者としての感覚を持って欲しいと思ったからです。社員一人一人が利益を追求していくという会社でなければ、今後の生き残りは厳しいでしょう。営業も工場も、全員がこの仕事ではどのくらいの利益が出るのか、出さなければならないのかを知ることで、会社は変わりますし、社員も変わります。多くの会社・社員が「売り上げ至上主義」に陥りやすく、そうなった会社は消えていくことが多いのです。
現在コロナ禍の影響で、印刷業界は厳しい状態にあります。そして仕事が少なくなると、多くの会社が需要のありそうな仕事に集中してしまいます。印刷通販などが今そうですし、かつてはストックフォームや道路公団のチケットなどがそれでした。そして、売り上げ欲しさに安値を売りにしてしまうのです。
ちなみにゲームでは、安値で出せば負けるので、安易な金額は出せなくなります。さらには単価を上げるにあたっては、仕掛けが必要ということを学ぶのです。
――心に残った講演をお教えいただき、その理由も教えてください
数多くあり、どれも心に残っていますが、就任して最初にお呼びしたのは、2008年4月発刊の「日本でいちばん大切にしたい会社」の著者で、法政大学坂本光司教授の講演でした。この流れから、同書で紹介され、障がい者の採用に関して、先進的な取り組みをされた日本理化学工業の大山泰弘会長に2011年に講演していただきました。
2009年には、林田正光氏による「リッツカールトン感動を呼ぶサービスの神髄」を開催し、企業として社会的な存在価値、社員として働く意義を問い掛けていただきました。
2014年の新春講演会では講師のお父様がトッパンムーアの副社長をされていた関係で、経営共創基盤CEOの冨山和彦氏から「今という時代と経営者の使命」をテーマに講演していただきました(今年6月には「コーポレート・トランスフォーメーション」を発刊)。

感動を呼んだ一人芝居『決断 命のビザ~杉原千畝物語~』
異色の企画では、エンターテインメント系の演劇『決断 命のビザ~杉原千畝物語~』を俳優で私の友人の水澤心吾氏が一人芝居で演じてくれました。外交官としての規律より人道を選択した杉原千畝の決断と実行力が、今の私たちに訴えかけるものがあるという思いからです。
どの講演も「企業の存在意義」「社会的な価値」「社員の気概」「社員が一個人としてのコンプライアンス」などを問う内容です。今の企業は、社員一人一人がこれらの規範を持っていないと、全体が崩壊すると私は考えますし、しっかりと実現させれば大きなブランド力になります。
いずれも、一社での取り組みは難しいものが多く、複数の企業が連携して行うことが必要になっています。そのきっかけづくりをしてきたのが、これらの講演だったと思っています。
――さまざまなセミナーやワークショップもありました。心に残ったもの、特に反応が良かったものがあればお教えください
先ほどの話ともつながりますが、梅津光弘准教授によるケースメソッドによるコンプライアンス研修は心に残りました。団体の連帯活動の推進について、社員一人一人のコンプライアンス意識について、お話しいただきました。
また、組織を率いるリーダーやマネジメントを行う社員には、インティグリティ「誠実」「真摯」「高潔」が重要な資質であることを教えていただきました。
2013年には「クレイグ氏のFMクレド」セミナーを開催。FM業務の改善、顧客への業務 の提案(BPO等)への方向性を示しました。サービス産業につながるファシリティマネジメントによる企業経営連続講座でした。
また、先ほどお話しした「MQ管理会計」勉強会も、いい内容なので続けてほしいです。
――フォーム業界はこの12年間でどこが変わり、どこが変わらなかったでしょうか
ビジネスフォーム印刷からデータプリントサービス(DPS)(BPO事業を含む)を含んだ売り上げが上昇しましたね。統計的には、ビジネスフォーム印刷の落ち込みを、データプリント分野が補う形でした。しかし、これも2年ほど前から補えない状況になっています。やはり、急速にデジタル化が進み、印刷の衰退が懸念されていましたが、その影響が出てしまっているようです。
ただ、今回の特別定額給付金の支給でも分かりますが、まだまだ情報印刷分野としてのビジネスフォームへの社会的な依存部分と存在意義は大きいものがあると感じますし、その根幹部分は変わりません。
給付金の申請書も、フォーム印刷業界がなければ届きませんよ。
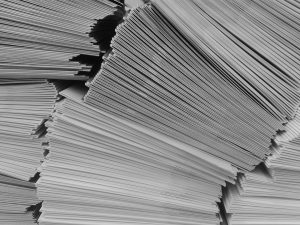
ただ、それだけではいけないので、情報系のサービスはもちろん、トランスプロモやDPSを含めたダイレクトメールなど幅広くカバーする必要があります。トランスプロモビジネスとして請求明細や利用明細もただ送付するのではなく、企業とその顧客に紐づいたダイレクトメール的な使い方をもっと提案すべきでしょう。
――印刷業界全体ではどうでしょうか
印刷業界全体は、非常に厳しい状況と考えます。
印刷市場が「少ロット」「多品種」「パーソナル印刷」に大きく変化する中、日本の多くの印刷会社が「大量印刷」「低価格路線」を踏襲してしまったことは大変残念なことです。
この一つの要因は、MQ会計の説明の時にも申し上げた「売上高至上主義」に固執し、「品種別損益管理」がなされていないことにあるように思います。
印刷業界では、オフ輪(オフセット輪転機)の占有率が40%と言われていますが、そのオフ輪の仕事が減っています。
コロナ禍で、新聞折込が急速に減退しました。ポスターやチラシも、飲食店や商業施設の営業自粛、展示会・スポーツ・エンタメイベントの中止・延期など、多くの経済活動が止まる中で激減しました。本当に各社厳しいと思います。

印刷するということの本質が問われている時代に急になってしまいました。
では「印刷業の本質とは何か」という話になるのですが、印刷はお客さんに「コンテンツを届ける仕事」です。今までは、情報としてのコンテンツを届けていた方法が印刷だったのです。
文章でも、写真でも、イラストでも、そのコンテンツを届けて、情報を伝える仕事は、かつては印刷しかなかった。しかし、インターネットの出現で大きく変化しました。
今後、我々はこれらの情報を、印刷にこだわらず届けていかなければならないと思います。動画でも、音声でもまったくこだわらず、印刷がメインストリームだなどと考えずに、手がければならないでしょう。
ただし、印刷とそれに関わるデータを扱う技術は、他に代わるところはないと考えています。そこを手放さずにいかに生かしていくかも問われると思います。
――フォーム工連の今後にどのような期待をしますか
もう一社だけでビジネスを継続する時代ではないと思います。一昨年から進めている「寺子屋教育」もこの流れの中にあり、繰り返しますが「企業間の連帯」がテーマの一つです。

「寺子屋」について発表する櫻井醜前会長
海外情報として情報発信をしている米国オハイオ州にあるProforma社の紹介や、会員企業が自由に使用することができるオープンプラットフォームの提供なども継続していってほしいと考えます。
あとは年寄りがいつまでも頑張らないこと(笑)。私も退任致しましたが、今後はITリテラシーを持った若い世代に任せることが大事だと思います。
――印刷業界全体ではどうでしょうか
もう7年前に掲げた事項ですが、印刷産業全体でも、以下のような方向性をもって欲しいと願っています。
・事業計画ではなく市場の変化に注視する
・評価基準を変えること
・市場調査を鵜呑みにしないで、自ら調べること
・印刷関連の設備投資は慎重にすること
・原価償却した印刷設備は廃棄すること(永遠に設備更新が行えない)
・デジタルプリントは印刷業界の救世主ではない
・印刷企業はコミュニケーションプロバイダーへの脱皮を
・外部の人材の活用
・新規事業を従来事業に統合させるな!
・失敗を許容する風土を創れ!
――最後に新型コロナウイルスで影響を受けている業界関係者へ、ひと言メッセージをお願いします
新型コロナウイルスにより、大きな変革を迎える時代となってしまいました。一方、大きく遅れているデジタル化が一気に進む予感がします。印刷分野の情報産業を担ってきたビジネスフォーム業界も、社会インフラとして進むデジタル化を、どのように捉えて進んで行くかが、各企業の明暗を分けることでしょう。
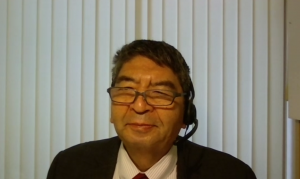
そこで、現在のコアビジネスを踏襲しつつ、デジタル化時代に即した経営者や経営陣をそろえて行くことが急務だと感じますし、会社を作り変える「コーポレート・トランスフォーメーション(CX)」のチャンスだと思います。
RPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)を行うことも必要になってきますが、この時に自分の業務をしっかり分解して考えられなければ、ロボットやAIに、仕事を任せることもできないのです。
繰り返しますが、印刷を軸足にするというのは間違ってはいけません。その仕事というのは、専門業者が明らかに強い。簡単に言うならIT業界の人に、印刷はできないでしょ?
コロナといえば、今回の特別給付金申込書で、余計な場所にチェックを付けてしまい、給付されないといった間違いが多く発生したそうです。このような社会的な問題を自分の仕事と思うかどうか、これが業界に求められていることだと思います。
私はフォーム工連を去りますが、別の形で協力できればありがたいですし、必要とあればいつでも駆け付けます。
12年間、皆さんのご協力をいただき、本当にありがとうございました。
最後の取材は新型コロナウイルスの影響を受けてしまい、インタビューがオンラインという形になった。残念であると同時に、最新の情報やツールを常に取り入れてきた山口さんらしいインタビューとなったとも思う。
実は前の会社を辞めて、今の仕事をし始めたのも、山口さんに教えていただいたさまざまなセミナーや書籍、人達との出会いの影響が大きい。と言うと「え~責任を感じちゃうなあ」といつも頭を掻いておられた姿を思い出す。
そのお人柄、先見性、真摯な取り組み、業界内外で知らぬ人はない重要な方。つい最近も、ある現役バリバリでITにも強い方から「あの人に敵う人はいない。皆が背中を追いかけている」との話を聞いたばかり。なので「さよなら」ではなく、きっと新たな登場の仕方で私の前に現れる気がしてなならない。
山口さん、本当にありがとうございました!
(プリント&プロモーション 中村)
Copyright © 2026 プリント&プロモーション . ALL Rights Reserved.