【2025年4月21日】昨年、2024年は8年ぶりに「drupa」が開催され、多くのメーカーが最新のデジタル印刷機を展示。多くの人がデジタル印刷の未来を考える年となった。
その中で読者からは「実際のデジタル印刷の現場はどうなのか?」「デジタル印刷を使ったビジネスはどう進んでいくのか?」という声があった。
そこで「デジタルプリント潮流」のテーマで、改めて日本の印刷会社を取材し、その現状をレポートしていく。
第5弾はデジタル印刷機やインクジェットプリンタを導入し、さまざまなプリンティングにチャレンジしているコトブキ印刷を訪問。江幡修社長、導入に関わった若菜真取締役、工務部で立ち上げを行った高信正男氏に話を聞いた。
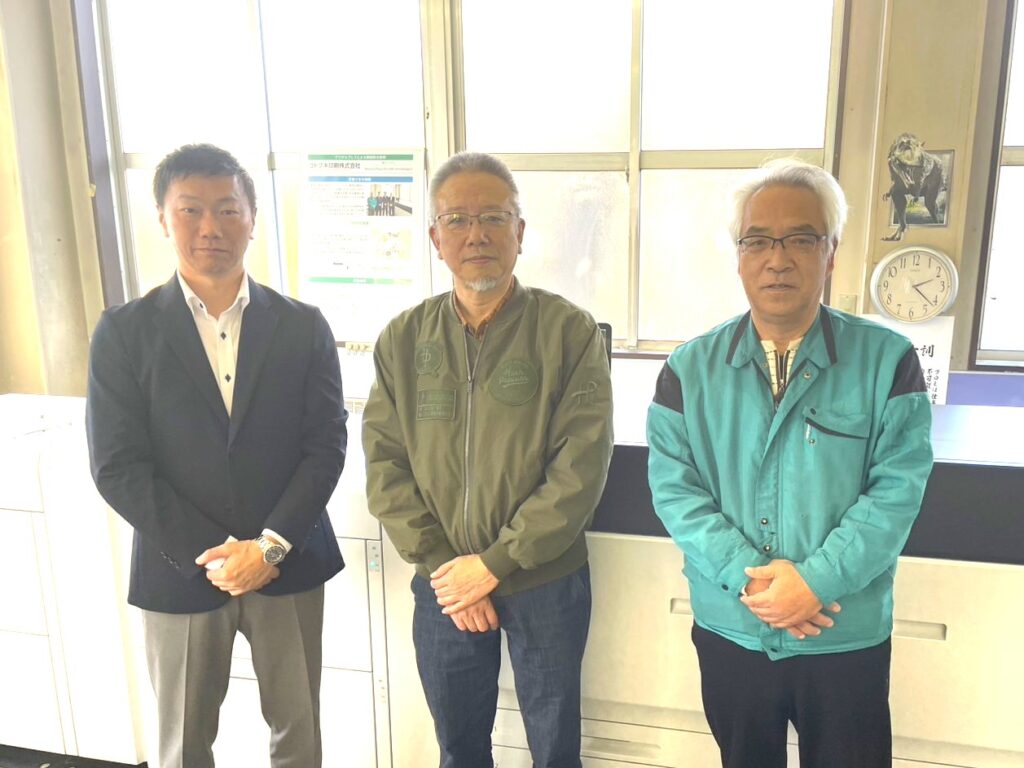
中央が江幡修社長、若菜真取締役(左) 工務部の高信正男氏(右)
コトブキ印刷は水戸市に本社を構える印刷会社。チラシやポスター、パンフレットなどの商業印刷から、名刺や封筒印刷、ハガキのほか、ノベルティーの制作も行う。
2023年11月に富士フイルムビジネスイノベーションフルカラープロダクションプリンター「Revoria Press EC1100」を導入し、デジタル印刷機を中心としたワークフローの構築を成功させた。

――貴社の歴史を教えてください
江幡 当社は1951年創業で、商業印刷を中心に名刺や封筒などを製造する印刷会社です。私が入社した頃はタイプライターや写植で打った文章で、自治体の広報などの印刷をしていました。版下作成から写真を貼って、ネガフィルムをつくるといった作業もしていましたね。当時は他社にカラー分解をしてもらって、2色機で2回通して印刷するといった時代でした。私は写植機から電算写植の導入そしてDTPへの移行などを見てきました。現在は小森コーポレーションの「リスロン」とリョービMHIグラフィックテクノロジーの「680X」という菊半サイズ4色機を持っています。

――江幡社長は印刷への強い思いがあるそうですね
江幡 今は印刷が否定されやすい時代です。政府のデジタル化推進や電子帳簿保存法などの新しい法律で印刷すること、紙を使うことが悪いことのようにされる風潮があります。時代の流れなので仕方ない部分はありますが、印刷を悪者のように扱われるのは、間違っていると感じているのです。
――確かに印刷が悪者にされてしまうような風潮はおかしいですね。その中でデジタル印刷機を導入されたそうですね。導入の目的などは?
江幡 2023年11月に富士フイルムビジネスイノベーション(富士フイルムBI)のプロダクションプリンタ「Revoria Press EC1100」を北関東で初めて導入しました。当社は、ナンバリング入り複写伝票を多く扱っているのですが、ナンバリング用の機械部分が壊れてしまい、その機械の製造元もすでになくなり修理もできない、中古を探したのですがこれもないという状況でした。さらに企業・団体などの報告書といった少量の印刷物が増えていたことから、デジタル印刷機の導入を検討し始めました。
――「Revoria Press EC1100」に決定された理由は?
江幡 販売代理店さんなどにさまざまな相談に乗ってもらい決定しました。実際に選定にあたった若菜に聞いてみてください。
若菜 ナンバリング装置の故障という大問題があったのですが、約1年かけて選定させてもらいました。社長からは「このデジタル機がいいという、その理由を私に説得・説明できるようにしてほしい」と言われていたので、それをしっかり押さえながら選定しました。まずはモノクロに強いこと、伝票は感圧紙が多いので「薄紙にも印刷できる」というのがマストの条件でした。
一般的に従来のデジタル印刷機は、薄物を得意としていなかったので、選定の最初の段階で、できるものは限られていました。
江幡 薄紙ができると同時に、モノクロ印刷品質は非常に高く、1時間にA4サイズで片面3000枚という速度も良かった。トータルにハイレベルというのが「Revoria Press EC1100」の印象です。

――最初から薄物ができるのはすごいですね
若菜 他社の製品では、まず薄物は刷れないという返事があり、刷れたとしても相当の工夫や改造が必要と言われ、そういった機種はその時点で候補から外しました。もちろん、伝票という非常に気を使うものですので、当社の方でも実験を繰り返し、これなら商品にできるというところまで詰めていきました。
江幡 あとは富士フイルムBIさんの担当者のフットワークがよかったですね。
――保守サービスなどは、小回りが利くのがいいですよね
江幡 その点は現場で立ち上げにかかわった高信がお話します。
高信 富士さんは、近隣に営業所があり、よく来てくれます。長年の信頼関係があるので、その点もデジタル印刷機選定のファクターになりました。同社は営業車に部品を全部積んでおり、対応も早い、徹底的に直してくれますので安心感があります。
――立ち上げにはどのくらいの時間がかかりましたか
高信 1年ほどはかかりました。メーカーは感圧紙のことを完全に理解しているわけではないので、どの用紙は可能で、どの用紙は不可能かということを1年かけて実験していったということです。
ナンバリングは、オフセット印刷機で刷ったものへの追い刷りを行う作業を想定しており、伝票を印刷機内に通さなければならないのです。また感圧紙の場合、熱で反応することもあるので、それもチェックしました。
通る通らないのほかで、難しかったのは見当合わせですね。どうしてもトンボが毛一本ずれるというようなことが起こり、この部分の修正に時間がかかりました。
若菜 オフとデジタルの混合は珍しいのですが、何かを刷った上から、デジタルでモノクロのナンバリングをしていくというのはかなりハードルが高いのです。先にミシンを入れてからの丁合になり、これも難しい。このため、当初は1時間3000枚できる機種なのに、1日3000枚しか印刷できませんでした。
――それは大変ですね。メーカーさんに対してはなんと?
江幡 この辺りの苦労は、メーカーさんとうちで二人三脚で実験しているという感じなので、一緒にやってくれてありがたかったという思いですね。
――今はどのくらいの枚数を生産されていますか
高信 最大で月間30万枚をカウントしたこともあります、平均では20万枚くらいですね。ページ物を通せば数は出せるのですが、少数ロットの名刺等もやっているのでこのくらいの数字になります。

江幡 高信は元工場長で、定年後もお願いして働いてもらっています。伝票の印刷を知り尽くした彼がやることで機械の性能を引き出してくれたとも感じます。
高信もそうですがオフセット印刷のオペレーターは年齢が高く、若い人の教育も大変で、2~3年かけてやっと操作をおぼえたくらいに離職してしまうなどといった課題がありました。デジタル印刷機はオフセット印刷に比べて半分くらいの教育期間で済みますし、ある意味誰でも扱えます。つきっきりでなくても生産できますし、ローラーの交換や版のかけ替えなどもないため非力な人でも扱える。オフセットよりも人的負担が少ないのは間違いありません。高信が不在の時はデジタル印刷機は、普段、後加工・製本担当の女性オペレーターが動かしています。
若菜 一方ですべてデジタル印刷でできるかというと、数万単位の仕事はオフの方が圧倒的に早いし、コストパフォーマンスもいい。なので、オフとデジタルをうまく併用していくという扱い方が必要だと思います。
――オフとデジタルの使い分けはどのように?
若菜 200冊前後までがデジタルで、それ以上はオフというのが当社積算上の大まかな目安。あとは先ほども言いましたようにナンバリングはデジタルですね。
――実際使ってみて便利な点は?
江幡 丁合をとりながらできるところはいいですね。昔は製本丁合機でやっていたんですが、ジャムると大変でした。また100%ナンバーと中身があっていることもデジタルのいい点です。機械式だと2個進むとか、半分進むといった不具合もありました。ナンバーの大きさも桁数も自由に設定できる点も素晴らしいです。
――デジタル印刷機を使ったユニークな印刷物があるそうですね
江幡 領収証に美しいデザインを施したオリジナル領収証や、千社札シールなどをデジタル印刷機で作っています。こういたものは印刷の力を表現できるもので、楽しさとともにPR効果があると思っています。これはデジタル印刷機ではないですが、エプソンのガーメントプリンタを導入してTシャツのプリントなども行っています。
――今後の展開は?
若菜 社長がオフセット機を出して、デジタル機をもう1台入れようという話をしています。まだ計画段階なのでいつということはないのですが…。
江幡 いやいや、今、自分が印刷業を始めるとしたらアナログの印刷機は入れないとう話です。デジタル印刷は比較的スキルがいらない。さらには「きつい・汚い・危険」といった3Kのイメージを払しょくできるのではないかという期待もあります。
デジタル印刷だけにこだわることはしませんが、できることが多く、さまざまな提案ができる。少量でユニークな製品をつくってユーザーに提案し、そこから新たなビジネスにつながる可能性があると思うのです。
我々がつくる印刷物はユーザーの先のお客様を呼ぶツールです.そのツールが「楽しいね。珍しいね。効果があるね」と言ってもらえるように活用していきたいと考えています。
Copyright © 2025 プリント&プロモーション . ALL Rights Reserved.